鬼姫奇譚 三章:遺恨
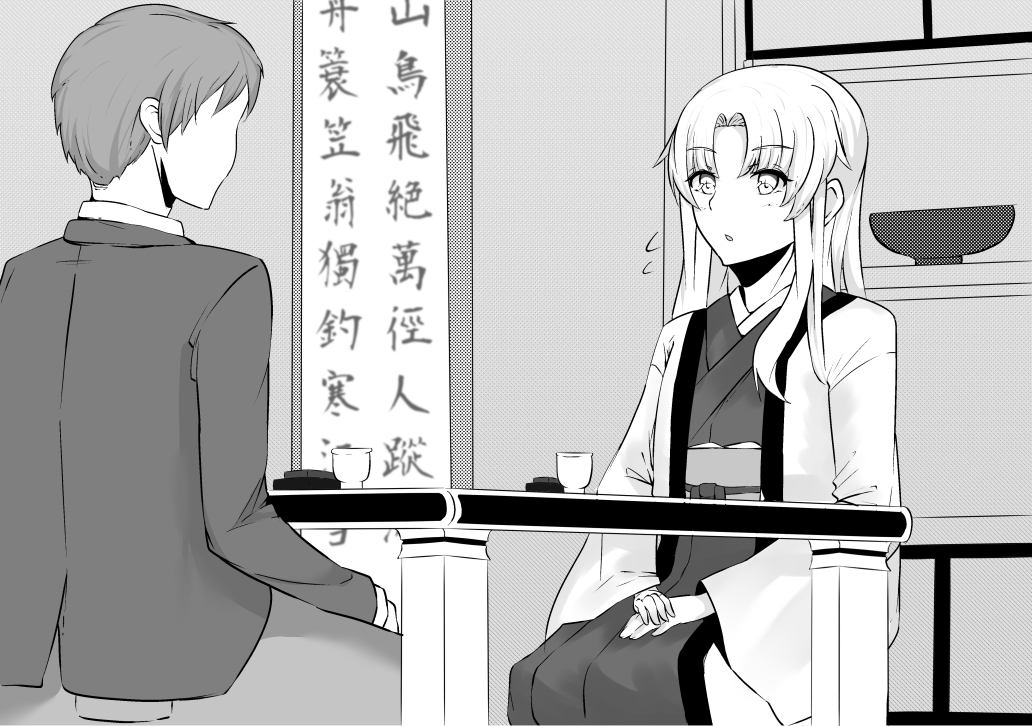
「これは聡文が語ったことですが、彼、いえ彼らの最終的な目的はかつて自分たちを亡き者にしようとした者への報復を行うことみたいです」
千方院邸の応接間。相変わらず梅の香しい匂いが部屋を薄っすらと包み込んでいる。昨日の襲撃にも関わらず、屋敷や庭への被害は皆無のようだった。
「亡き者に?」
「ええ。以前、私達千方院家のことを簡単にお話ししたかと思うのですが、その話には少し続きがございます」
明治期に一度瓦解の危機に瀕した千方院家は、八重千代を始めとする家の者達の尽力によりどうにかその命脈を保つことが出来た。
しかし、その過程で離散した者達がいた。彼らの中には、新しい時代の中でそれに合わせた生き方を見つけ、独立してやっていく者もいたが、大半の者にとって、離散の意味は過去との決別ではなく、反抗の意思表示であった。聡文もその一人である。
彼らは、他の同様な境遇の者達を取り込み、いとも簡単に自分たちを切り捨ててしまった者達へと非難を浴びせた。これではあんまりだ、これまで影として身を粉にして仕えてきたというのに、何故こうもあっさりと自分たちは捨てられるのか。理不尽の極みだ、と。彼らの主張はもっともではあったが、しかし、押し殺すべき主張であった。
日に日に増していく彼らの不満に時の権力者達は危険性を感じ、何度か警告をした。
「その時点であればまだ引き返しは出来たのだと思います。弓司庁には千方院家の者である秀明という男がいて、彼のとりなしもあり彼らに対する妥協案は用意されておりました。しかし、聡文達は後には引かなかった。彼らは、徹底抗戦を唱え、人の世界で武士が反乱を起こしたように、政府に反旗を翻しました。このことは歴史の表舞台には一切記録を残してはいませんが、その戦いは、一方的なものだったと聞きます」
大敗を喫した聡文達は、全滅こそしなかったものの歴史の裏の舞台からも姿を消すことになった。それ以降、彼らが何処に行ったかはようとして知れなかった。
「幸い聡文達は自分たちの新天地を見つけたようでしたが、しかし未だ不満を持ち続けているのだと思います。だから、かつて自分たちをないがしろにした者への報復を考えている」
「ただ仕返しをしに行ったのでは前回の二の舞だ。だから、そのための切り札の一つが八津鏡なんですかね」
「恐らくは。彼らの気持ちは分からないものでもないのですが、かといって許されることでもありません。一刻も早く八津鏡を取り戻し、彼らを止めてしまわないと大変な事なる可能性があります」
八重千代の拳に力が入る。きっと、八重千代はこれまでずっと耐えてきたのであろう、と天野は思った。ある意味で使い捨てにされた自分達の境遇のこと、聡文達が離反したこと、そして同胞が蹂躙されたこと。それ以外にも何かあったかもしれない。憤怒に駆られることもあったかもしれないその日々を、八重千代は今日の今日まで耐えてきた。そして今回もその気持ちを押し殺して聡文達を止めようとしているのか。
「彼らが何処にいるかの見当は付いてますか」
「いいえ、確実な所はまだ。ただ」
「ただ?」
「聡文がこんなことを言っていました。『仙涯郷に来れば人里でコソコソと生きる必要もない』と」
「せんがいきょう、ですか。なんなんですかね、それは」
「昔、噂に聞いたことがあります。なんでもそこは、思わず息を呑むような色彩絵巻の光景が広がっているとか」
「ほう。まるで竜宮城や蓬莱の島のような?」
「おそらくはそのようなかんじでしょうか。しかし、そこは人でないものが跳梁跋扈している異界の楽園とも言われております」
「人は招かれざる客、かね」
「さて。それは分かりませぬが、いずれにせよ彼らは自分達の住んでいる所をそう呼んでいるようです」
「ふむ、少しは手がかりになるかね。八重千代殿」
「はい、なんでしょう?」
「これから少々お付き合いいただけますか?」
それを聞いた途端、八重千代は困ったように赤らめた顔を手で覆い隠す。
「え? あ、あの。困ります。そんなこと突然に」
「ああ、い、いえ、すみませんそういう意味ではなく」
状況を把握した天野は必死に手振り身振りで弁明する。
そんな天野の様子に耐えかねたように、八重千代が笑みがこぼれだす。
「クスクス。先生、本当に面白い人」
「え?」
突然の八重千代の態度の豹変に天野は思わず素っ頓狂な声を出した。
「冗談です。先生がそういった方でないことは先刻承知でございます。ですので」
「で、ですので?」
「一計を案じてみました。先生は真に悪戯甲斐のあるお方です。つまり大変貴重な逸材ですね」
わ、訳が分からない。天野は困惑する。
「と、とにかく」
「ええ。是非ともご同行させてくださいまし」
千方院邸の応接間。相変わらず梅の香しい匂いが部屋を薄っすらと包み込んでいる。昨日の襲撃にも関わらず、屋敷や庭への被害は皆無のようだった。
「亡き者に?」
「ええ。以前、私達千方院家のことを簡単にお話ししたかと思うのですが、その話には少し続きがございます」
明治期に一度瓦解の危機に瀕した千方院家は、八重千代を始めとする家の者達の尽力によりどうにかその命脈を保つことが出来た。
しかし、その過程で離散した者達がいた。彼らの中には、新しい時代の中でそれに合わせた生き方を見つけ、独立してやっていく者もいたが、大半の者にとって、離散の意味は過去との決別ではなく、反抗の意思表示であった。聡文もその一人である。
彼らは、他の同様な境遇の者達を取り込み、いとも簡単に自分たちを切り捨ててしまった者達へと非難を浴びせた。これではあんまりだ、これまで影として身を粉にして仕えてきたというのに、何故こうもあっさりと自分たちは捨てられるのか。理不尽の極みだ、と。彼らの主張はもっともではあったが、しかし、押し殺すべき主張であった。
日に日に増していく彼らの不満に時の権力者達は危険性を感じ、何度か警告をした。
「その時点であればまだ引き返しは出来たのだと思います。弓司庁には千方院家の者である秀明という男がいて、彼のとりなしもあり彼らに対する妥協案は用意されておりました。しかし、聡文達は後には引かなかった。彼らは、徹底抗戦を唱え、人の世界で武士が反乱を起こしたように、政府に反旗を翻しました。このことは歴史の表舞台には一切記録を残してはいませんが、その戦いは、一方的なものだったと聞きます」
大敗を喫した聡文達は、全滅こそしなかったものの歴史の裏の舞台からも姿を消すことになった。それ以降、彼らが何処に行ったかはようとして知れなかった。
「幸い聡文達は自分たちの新天地を見つけたようでしたが、しかし未だ不満を持ち続けているのだと思います。だから、かつて自分たちをないがしろにした者への報復を考えている」
「ただ仕返しをしに行ったのでは前回の二の舞だ。だから、そのための切り札の一つが八津鏡なんですかね」
「恐らくは。彼らの気持ちは分からないものでもないのですが、かといって許されることでもありません。一刻も早く八津鏡を取り戻し、彼らを止めてしまわないと大変な事なる可能性があります」
八重千代の拳に力が入る。きっと、八重千代はこれまでずっと耐えてきたのであろう、と天野は思った。ある意味で使い捨てにされた自分達の境遇のこと、聡文達が離反したこと、そして同胞が蹂躙されたこと。それ以外にも何かあったかもしれない。憤怒に駆られることもあったかもしれないその日々を、八重千代は今日の今日まで耐えてきた。そして今回もその気持ちを押し殺して聡文達を止めようとしているのか。
「彼らが何処にいるかの見当は付いてますか」
「いいえ、確実な所はまだ。ただ」
「ただ?」
「聡文がこんなことを言っていました。『仙涯郷に来れば人里でコソコソと生きる必要もない』と」
「せんがいきょう、ですか。なんなんですかね、それは」
「昔、噂に聞いたことがあります。なんでもそこは、思わず息を呑むような色彩絵巻の光景が広がっているとか」
「ほう。まるで竜宮城や蓬莱の島のような?」
「おそらくはそのようなかんじでしょうか。しかし、そこは人でないものが跳梁跋扈している異界の楽園とも言われております」
「人は招かれざる客、かね」
「さて。それは分かりませぬが、いずれにせよ彼らは自分達の住んでいる所をそう呼んでいるようです」
「ふむ、少しは手がかりになるかね。八重千代殿」
「はい、なんでしょう?」
「これから少々お付き合いいただけますか?」
それを聞いた途端、八重千代は困ったように赤らめた顔を手で覆い隠す。
「え? あ、あの。困ります。そんなこと突然に」
「ああ、い、いえ、すみませんそういう意味ではなく」
状況を把握した天野は必死に手振り身振りで弁明する。
そんな天野の様子に耐えかねたように、八重千代が笑みがこぼれだす。
「クスクス。先生、本当に面白い人」
「え?」
突然の八重千代の態度の豹変に天野は思わず素っ頓狂な声を出した。
「冗談です。先生がそういった方でないことは先刻承知でございます。ですので」
「で、ですので?」
「一計を案じてみました。先生は真に悪戯甲斐のあるお方です。つまり大変貴重な逸材ですね」
わ、訳が分からない。天野は困惑する。
「と、とにかく」
「ええ。是非ともご同行させてくださいまし」